👤宮本佳世乃
第35回現代俳句新人賞2017年度受賞
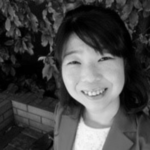 ひかりごと
ひかりごと
ひかりごと腹に納まり秋茄子
雲ひとつなき白露を聞いてゐる
望の月波打ち際の濡れさうに
ぼそぼそと裂け始めたる芭蕉かな
鈴虫やふたたび生まれては来ぬか
一人旅が好きだ。
二十歳代のころから、怖いもの知らずも手伝って国内外を旅した。
気ままな思いつきで予定を決める、その無頼の愉しさに魅かれてきた。
けれども現実は、交通の便や外食の時間など、思い通りにならないことも多い。
身軽なはずの一人旅でさえ、気づけば知らず知らずのうちに「こうでなければ」という思い込みや、サーカディアンリズムに従って日々を過ごしている自分がいる。
朝に目覚め、日中は動き回り、湯に浸かって夜は眠る。
非日常な一日を夢見つつも、結局はいつもと変わらない。
それでもどこかで納得している自分も可笑しく思える。
いつか、自分でも驚くような冒険をしてみたいものである。
この秋、二十三年を過ごした結社を退会した。
人生の幾割かを丸ごと俳句や結社の活動に費やせたのは、この上なく幸せなことだった。
今後の身の振り方は未定。
この宙ぶらりんな時間こそ、不思議と心を弾ませてくれる。
またどこかにふらっと行きたいな。鞄一つだけ持って。
「ひかりごと」5句を読む
👤永井潮
▶ひかりごと腹に納まり秋茄子
ひかりはかな書きだが多分光だろう。秋茄子が光と共に誰かのお腹に納まったところ。連用形でこれからどうなるのか。秋茄子は身が締まって味が良いので嫁に食わすなという何とも酷いことわざがあるが、この句は意識しての秋茄子だろうか。ただ調理する前の茄子は光を放っているかもしれないが、調理済みのものを食べるのだから上五中七はどういう意味だろう。人以外の動物なら光ごと丸呑みもできるが不自然。光が味とか香りとか盛り付けあるいは新鮮さの比喩になっているのかもしれないがどうも読みに自信がない。
▶雲ひとつなき白露を聞いてゐる
白露は夜明けから太陽により溶けて無くなるまでのわずかの間の命の露だ。白露を聞くというのは無数の小さな水滴があたかも音あるいは声を出していると感じたのかもしれない。明け初めた空には雲の姿がない。
▶望の月波打ち際の濡れさうに
中七は海辺や湖畔などすぐそこまで波が打ち寄せているところだが、その辺りは常に濡れているものだ。望の月との対比で明暗を際立たせている。濡れているところをさらに濡れそうだと言って一句が成立する。
▶ぼそぼそと裂け始めたる芭蕉かな
近くの畑の隅に十本くらい二か所向かい合って芭蕉が植えてある。夏はかなりの高さに葉を拡げるが芭蕉は草なのだそうだ。裂け始めたのは葉、上五は水気の少ない状態か小声で物を言っているように感じたのか。俳聖のことも頭にあったのだろう。
▶鈴虫やふたたび生まれては来ぬか
鈴虫やの後の小さな沈黙は鈴虫への呼びかけか。あるいは同胞への連帯か。下五は「来ないのか」希望的に「来ませんか」と読みの選択を迫られる。
永井潮
昭和12年生まれ
初学は「季節」金尾梅の門に師事
鈴木勁草の同人誌「礁」に参加
「ロマネコンティ」同人
現代俳句協会会員
多摩地区現代俳句協会副会長
👤永井潮
第1回「風を詠む」年間賞大賞2025年受賞
 肉食恐竜
肉食恐竜
おおもとに肉食恐竜生身魂
夕立が来て豚肉を売り急ぐ
国産のレモンは絞り器が嫌い
尾骨まで残暑のとどく丸の内
受付を通らず白い秋が来た
かつての俳人のように暮らしの中から俳句を作るのは難しい。
ほとんどのシーンは言い尽くされて新しさを感じる句にはなかなか出会えない。
隙間産業という仕事に似ている。とは言ってもあまり形を崩してしまうのもまずい。
俳句のルーツは歌だから声に出して快い方が良い。
以前、市の教育委員会が小中学生の授業に俳句を取り入れることになって何度か教えた。
小学校の二年生の授業で、俳句について知っていることは、と聞くと「ごーしちごー」「きごー」とあちこちで声が上がる。
俳句を作る基本は比喩、擬人、対比から始めるといいと教えた。ただし対比は小学生には難しく中学生になってから。
柿食えば、の後の僅かな沈黙にある作者の思いは中学生でも理解が難しそうだった。
昨今いろいろな俳句を見るが、自作を含め読み終えた後で「あ、そう…」、「それでどうしたの?」、「どういう意味?」の三つの感想で終わる句が少なくない。読む力の貧しさのせいでもあるが特に三番目の感想が増えつつあってじれったい。
「肉食恐竜」5句を読む
👤宮本佳世乃
まずタイトルの「肉食恐竜」に心惹かれた。
この圧倒的な四文字熟語を目にしたとき、意味だけでなく、音に重厚感というべきか、ただならぬ様子が想像され、直観的に面白そうだと思った。
恐竜には肉食のものも植物食のものも、その両方である雑食もいるというが、ここでは「肉食」である。巨大な身体を動かすには、エネルギーが必要であり、その源が生命だということ。
タイトルは単に古代の巨大獣を指すだけでなく、生の本質や荒々しい生命力を思わせる言葉として機能し、各句の中でそれぞれの現実感、実在感を照らし出すための大きな枠組みとなっている。
▶おおもとに肉食恐竜生身魂
太古の肉食恐竜の獰猛さと「生身魂」の取り合わせ。文字どおり生命の根源的なエネルギーを強烈に呼び起こす句だ。
「生身魂」といえども矍鑠たる様子、特に食事の風景が浮かぶ。
▶夕立が来て豚肉を売り急ぐ
スーパーマーケットではなく、商店街の精肉店で食材を買い求めているのだろうか。
「夕立が来て」に市民の生活感がある。
夕立の急迫と販売者の慌ただしい動作の重なりが面白い。
▶国産のレモンは絞り器が嫌い
レモン絞り器には、居酒屋などでよく見かけるレモン自体をまわすものと、手動でプレスして圧縮するものの二種類がある。
この句は国産のレモンが主体。
国産のレモンに主張や感情を与えているが、確かに身体を搾り取られるのは痛そうで敵わない。
レモン絞り器という人工物から、現代生活の中のちょっとしたずれや異和感が現れる。
▶尾骨まで残暑のとどく丸の内
都会の残暑を身体感覚の深いレベルで捉えた句である。
丸の内というビジネスの中心地の熱気が、体の根底まで届くように感じられ、都市の環境と人間の身体感覚が切り離せないほどに一体化している張り詰めた空気を詠んでいる。
▶受付を通らず白い秋が来た
今年の夏は異常なほどに暑かったし、長かった。
それを「受付を通らず」としているのだろう。
「受付」というと、構築された制度や形式を思うけれど、そういったものに縛られず、秋がすうっと入ってきたのだ。
直接は関係ないだろうが、冒頭の「生身魂」がより白く透き通ったようにも思う。
とても面白い連作の締め方である。
宮本佳世乃(みやもと・かよの)
1974年東京生れ
2002年から俳句を始め、「炎環」で活動する
現在「オルガン」「豆の木」所属
句集に「鳥飛ぶ仕組み」「三〇一号室」
2017年 第35回現代俳句新人賞
