国際俳句に関わって8年
👤向瀬美音
私が国際俳句に関わって8年になる。具体的には「俳句ガーデン」という国際俳句グループの主宰をしている。この活動はフェイスブックを使って毎日世界の俳人と句会をしている。当初は100人にも満たないグループであったが今はあっという間に世界に広がりメンバーは4700人、国籍も40、そして毎日の投稿数も150を超える。私は毎日全ての句に目を通し、訳せるものは17音にしている。今やライフワークの一つになっている。
17音に訳すのは日本の俳人に海外の句を紹介するためである。そして17音にすると俳句の良さが増して海外の俳人と一層一体感が増すのである。
国際俳句に関わって新しい発見がどんどん出てくるがそれをポイントごとに纏めてみたい。
1.
国際俳句にルールなど要らないという人がいるが、私は最低限のルールは必要だと思う。なぜなら、文章をただ3行に並べると短詩になってしまうからである。最低限のルールは、一瞬を切り取る、具体的なものに託す、一箇所切れを入れる、省略を効せる、用言はできるだけ少なくするである。しかし、できたら俳句の中に一つ季語を入れる、取り合わせを試みる、である。一物仕立てももちろんいいが成功しにくい。
2.
次に季語についてだが、季節のない国もあるから国際俳句に季語は必要ないという人もいるが世界で季節の変化の顕著な国も多い。もちろん24節気を理解してもらうのは難しいが日本の歳時記の中の時候、天文、生活、動物、植物を、項目別によく見ると共有出来るものは多い。グループ結成1年目は、水、風、匂いといったキーワードで句を集めていたが、季語を紹介してはどうだろうかと考え、2年目から季語の欄を作った。そこに投句される句は膨大な量になった。もちろん季語の説明も加えてある。アンソロジーも1号から6号まではアルファベット順に編集していたが今はもう歳時記形式にしている。歳時記形式にするとメンバー同士も日本の俳人も見やすいし、なんと言っても同じ対象を愛で、同じ感慨に浸ることができるのである。
3.
次にシラブルの問題である。俳句は世界で一番短い17シラブルの3行詩である、というのが世界の共通認識である。しかし日本の俳句は17モーラである。シラブルというのは母音と子音の一塊である。これを英語、フランス語に当てはめて17シラブルの俳句を作ると、とても長くなってしまい、短詩のレベルになる。またイタリア語のように母音で終わる俳句にも適さない。しばしば指を折って17シラブルを数えている外国の俳人がいるが、それは、意味がないのである。第1項目の俳句の最低限のルールをしっかり当てはめてもらえばよい。西洋の小学校では14行からなるソネット言う詩を習うそうだが、それに比べると俳句は3行詩で、簡単だと思って始る人も多いだろう。また西洋詩の饒舌で抽象的な詩に飽き飽きしてシンプルな象徴詩に惹かれて入ってくる人もいるようである。
4.
次に内容のことであるが、取り合わせか一物仕立てなのかじっくり読んで見極める必要がある。最近は一物仕立て挑戦する人が多く、前書きに一物仕立てと書いてある。またモノクというものも流行っていて、ハイフンなしに一行詩を書いてくる。なるほど、俳句なのである。そして一物仕立てに適している。私は切れを表すためにハイフン使うことをすすめている。ハイフンのない一行詩は散文のように思える場合があるからである。
5.
このグループには、英語、フランス語、イタリア語、スペイン後、中国語で投稿される。それぞれの言語に長けた俳人が選句して訳しているのだが、そこにある各言語の、音節、韻、リズムはとても大事である 。
6.
世界は今や混迷を深め矛盾に溢れている。コロナ禍のちの世界紛争は激しい。俳句ガーデンにはヨーロッパ、チュニジア、モロッコ、アルジェリア、インド インドネシアの俳人が多いのだが、彼らの寄せる戦争詠には心に迫るものがある。子供と戦争を組み合わせた句が多いのである。海に囲まれた遠い島国の日本が戦争詠を読むと、それらはテレビ、Uチューブで見たものであり、他人事感が否めない。しかし外国の俳人の戦争詠は胸に迫ってくる。子供への慈愛の気持ちもよく共感できるのである。
7.
前にも述べたが、何より、俳句と短詩の違いをはっきりさせることが重要である。取り合わせの場合、そこに調和があるのか二物衝撃なのかを見分けるのも大切である。たまにはっとする二物衝撃に出会うが、これは日本人にも外国の俳人にも難しい課題だと思う。そして、取り合わせの場合、二つのものの間に横たわる深い沈黙、また、広大な響きを生み出すのは俳人の課題である。
8.
8年も国際俳句に関わっているとそれぞれの国の俳句の雰囲気もわかってくる。インド、インドネシア、などアジア圏の作品は即物的で日本人の作品に近い。チュニジア、モロッコ、アルジェリアはよく詩人の国だと言われるが、作品もとても詩的である。またフランス、イタリア人の作品には光、影、色が溢れている。まるで印象派の絵画を見ているようである。彼らは浮世絵に魅せられて俳句に入ってきたとも言われる。私は彼らの俳句にモネ、ゴッホ、シスレーなど印象派の絵画を見る。
9.
海外の俳人の俳句の知識は豊富でイタリア人は前書きに現代俳句と書いて俳句を投稿してくる。これは日常詠である。また、2行俳句、3行俳句、1行俳句、モノク、4行俳句と巧みである。
10.
私は昨年「パンデミック時代における国際俳句の苦悩と想像力」という本を出したが、これはこのグループで毎週行っている週間秀句鑑賞2020版を日本語に訳したものである。私は彼らの文章力, 鑑賞力、分析力、に驚いた。俳句は「句作と鑑賞という車の両輪 で成り立っている。」ということが浸透していると思った。西洋の子供たちは小学校から論評を書く訓練を受けており、文章を書くのが大好きで小論文は実に上手いのである。
11.
最後に、なぜ17音に訳すのかという問題だが、機関誌5号までは直訳で二行に並べていた。しかし、だんだん俳句が短くなり、17音にそのまま訳せるようになってきたのである。情報量が多い時は、無理である。しかし1項目の最小限のルールを守って句作をすると、17音に当てはまるのである。そして、日本人も海外の俳句に親しみを持てるのである。
12.
歳時記を作り始めると外国の俳人の好きな季語の傾向がわかってくる。アジア圏と西洋圏は少し違ってくる。米栽培を行う国と小麦栽培とに分かれる。アジア圏で刈田に人気があった。また 一般的に一番人気があるのは、月、天の川、流星、渡鳥、燕、蝶であった。海外の俳人は天文にとても敏感で鳥も蝶も花も大好きである。
『国際俳句歳時記 秋 -国境を越えた魂の震撼-』(コールサック社、2025年)からいくつかの句と彼らの俳句に対する意識をあげてみようと思う。
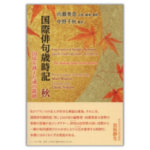
立秋や陽は優しさを編んでるやう
ローザ マリア サルバトーレ
(イタリア)
波立てるコーヒーカップ秋立つ日
アメルラディヒビ ベント チャディ
(チュニジア)
立秋や空にはためく紅白旗(インドネシア独立79年)
タンポポ アニス(インドネシア)
貝殻に海の怒涛を聞きて秋
アンジェラ ジオルダーノ(イタリア)
Autumn-the roar of the sea in the shells
秋めきて蒼白になる移民の顔
ソニア ベン アマール(チュニジア)
*地中海を渡ってくるアフリカ大陸の移民のことだろう。
青といふ青を極めて秋の空
ポール カルス(マルタ)
空つぽのベンチに秋が座している
ディミトリー シュクルク(スロベニア)
*禅の境地を感じる。
悲しき秋戦場の子は天使へと
クルッチ ヴィクトリア(イタリア)
*未だ続くウクライナ戦争、またはガザ地域の紛争のことだろう。
ガザの秋少女の瞼永遠に閉づ
ガブリエラ デ マシ(イタリア)
*これも心に迫る時事句である。
詰みチェスの逃げれぬやうな残暑かな
タンポポ アニス(インドネシア)
駅地下のカレーの匂ふ残暑かな
タンポポ アニス(インドネシア)
家系図をネットで調べたる秋分
フランソワーズ マリー チュイリエ
(フランス)
秋分や決勝チーム同じスコア
カディジャ エル ブルカディ
(チュニジア)
十月の夜空一つの星のため
スアド ハジリ(チュニジア)
各階にスープの匂ふ秋の暮
イザベル ラマンームニエ(フランス)
胡桃割りして過ごしたる秋の夜
エレナ ズアイン(ルーマニア)
長き夜や壁にランプの影差して
ダニエラ ミッソ(イタリア)
一列に並ぶカヤック秋澄めり
ナッキー クリスティジーノ
(インドネシア)
新涼や旅行チケット引き出しに
アブダラ ハジイ(モロッコ)
川底に転がる小石秋うらら
ダニエラ ミッソ(イタリア)
無関心な人々の影秋深し
クリスティーナ ブルビエンティ
(イタリア)
秋深し眠りに入りゆく大地
キム オルムタック (オランダ)
道化師の悲しき笑顔秋深し
タンポポアニス(インドネシア)
晩秋や祖父の時計の音のする
ダニエラ ミッソ(イタリア)
秋の日や蝶はその影踊らせて
ナディン レオン(フランス)
雌ライオン首の後ろに受く秋日
プロビール ギュプタ(インド)
秋の声遠くで誰か伐採す
ナッキー クリスティジーノ
(インドネシア)
空高し女の欲はきりがなく
バーバラ オルムタック(オランダ)
秋高し青き瞳の新生児
マフィズディン チュードハリ(インド)
水に溶くテンペラ絵の具鰯雲
ダニエラ ミッソ(イタリア)
ここまで、時候、天文のいくつかをあげたがこのような感じで 秋の歳時記は、2160句掲載した。
もう一つここで紹介したいのは、彼らの俳句感である。フランス人、イタリア人、マルタ人、モロッコ人、インドネシア人の俳人にそれぞれ書いてもらった。特に興味深かったのはフランスの俳人、ナディン レオンの文章である。ここに少し紹介しようと思う。
「俳句は伝統とモダニズムが融合した日本の美学であり、その基本原則の三つは象徴性、節制、空虚である。具体的で地味で、単純で日常的で自発的なもの全てを好むことによって暗黙のうちに感情を伝え、雰囲気を描くのが作者の技術である。この繊細な芸術は物事の儚さを感じさせたり(わびさび)、神秘的で不可解なものに美を感じさせたり(幽玄 )、繊細さを感じさせたり(しおり )、 ユーモアに軽妙さを感じさせたり(かるみ)、することができる。俳句では安定と進化という相反する二つの原理が共存している。安定は季語の使い方にあり、進化は作者のもの見方にある。」
以上、国際俳句グループ「俳句ガーデン」の活動のおおよそを述べさせていただいたが、最後に、今年3月に出版した『国際俳句歳時記 秋』続いて、8月には夏を完成させ『春』『夏』『秋』『冬』全4巻を完結した。
