蛇吐く歩き巫女
福島*斎藤秀雄
鏡沼ひたに蛇吐く歩き巫女 斎藤秀雄
特定の神社に属せず漂泊した巫女を歩き巫女という。祈祷し、口寄せをし、春をひさぐ神聖娼婦の一種だった。遊女の起源を巫女に求める説もある。
蛇はもっとも原初的な自然神のひとつ。水神であり、龍であり、虹(虹霓)でもある。富澤赤黄男・高柳重信がエロティックに描いた「身をそらす虹」も暗示されよう。「祭祀」の「祀」は自然神を祀ることで、自然神の代表的神格が「巳」である。蛇=神と交わる巫女を蛇巫という。蛇巫は縄文中期・勝坂式土器の女人土偶、古代ギリシャのディオニュソスの儀礼、奄美のノロなどに見られる。いずれも巫女・従者・女性信者が頭に蛇を巻き付けた姿を見せている。
.png)
福島県鏡石町の伝承が残る「鏡沼」(撮影:斎藤秀雄)
熊野の風鈴
和歌山*北岡ゆみ
鉄ふうりん熊野の風を取り込みて 北岡ゆみ
 熊野は和歌山県南部と三重県南部にかけての地域であるが、熊野三山(本宮大社、速玉大社、那智大社)を有し、紀伊山地の霊場として、古来より熊野信仰の中枢を担ってきた。ゆえに、この信仰深い土地に吹く風は、並みの風ではなく霊験あらたかな重厚な風である。そしてこの風をとり込むことのできる風鈴といえば、やはり鉄(くろがね)製であろう。熊野の風をとり込んだ鉄の風鈴は、魂を震わせるような音色を放ちながら、その音色を樹間に沁み込ませてゆくのである。
熊野は和歌山県南部と三重県南部にかけての地域であるが、熊野三山(本宮大社、速玉大社、那智大社)を有し、紀伊山地の霊場として、古来より熊野信仰の中枢を担ってきた。ゆえに、この信仰深い土地に吹く風は、並みの風ではなく霊験あらたかな重厚な風である。そしてこの風をとり込むことのできる風鈴といえば、やはり鉄(くろがね)製であろう。熊野の風をとり込んだ鉄の風鈴は、魂を震わせるような音色を放ちながら、その音色を樹間に沁み込ませてゆくのである。
又、風鈴はさておき、熊野は、様々な音が響くことによって詩が生まれる場所であり、空間である。
詩歌降るごとし熊野の夏鶯 川村祥子
.png)
那智の滝と青岸渡寺 (撮影:満田三椒)
管絃祭
広島*川崎益太郎
管絃祭清盛の海光らせて 木佐幸枝
「管絃祭」は、世界遺産に登録されている厳島神社の神事です。瀬戸内海の宮島に鎮座する「厳島神社」は、飛鳥時代に創建され、1168年(仁安3年)に武士の平清盛が運営した歴史ある神社です。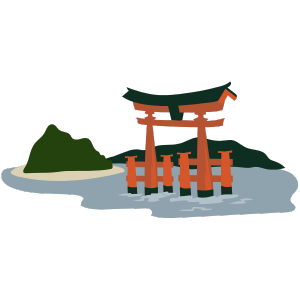
この厳島神社で、例年、旧暦の6月17日に開催されるのが「管絃祭」です。平安時代の貴族たちが水上で楽しんだ「管絃の遊び」を平清盛が厳島神社に移し、神様を慰める神事として、執り行うようになったといわれています。「日本三大船神事」のひとつとされています。
和船3隻をつないだ御座船が、瀬戸内海を渡って神事が、夕方から深夜にかけて行われます。日が暮れるにつれ、ゆっくりと空にあがった満月の光が、御座船を照らします。月明りの下、御座船で優雅な管弦の音色が奏でられる様子は、まさに清盛の海の威光のようです。
