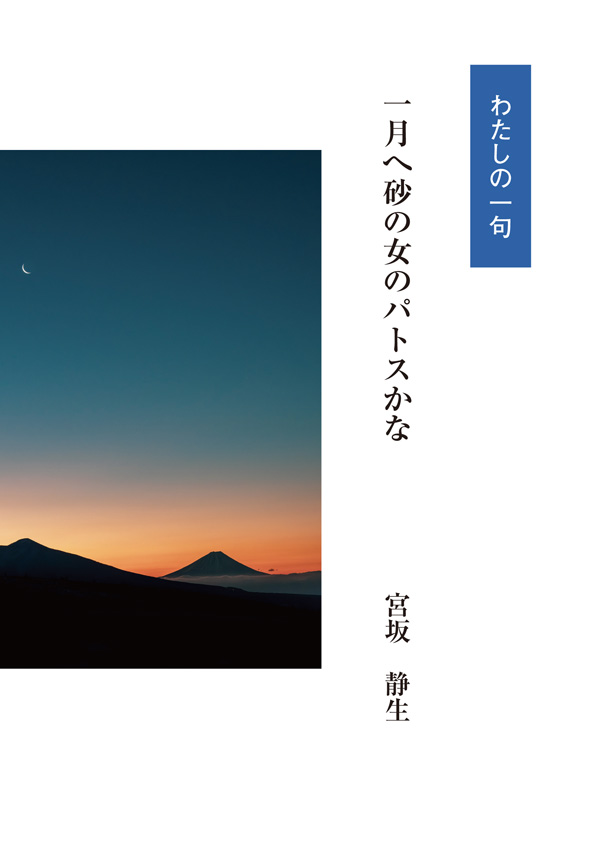
写真提供:岡井 剛
「わたしの1句」鑑賞 柳生正名
一気に読み下した時、読み手の内にどのようなイメージ的冒険が引き起こされるのか。そのドラマツルギーにどうしようもなく惹かれる一句ではないか。
〈砂の女〉はさまざまなイメージを喚起する。啄木ファンは、抱きしめるとさらさらと崩れ、腕の間から滑り落ちる存在を思うだろう。キリスト教の信仰をもつ者には、創世記ソドムとゴモラ滅亡のくだり。脱出したロトの妻は、神の言葉に背いて後ろを振り返り、「塩の柱」に変えられる。
安倍公房の読者なら代表作『砂の女』を思うはずだ。「飛砂におそわれ、埋もれていく、ある貧しい海辺の村」に囚われた男が、地の女と砂掻きに追われる生活を強いられる。脱出の情熱はやがて女と共にする日常への愛着へとすり替わる。その情念の変化の過程がスリリングだ。作家は自作について「『砂』というのは、むろん、女のことであり、男のことであり、そしてそれらを含む、このとらえがたい現代のすべてにほかありません」と語っている。
一方、〈パトス〉とは古代ギリシャ語で情熱・情念。掲句でも、パトスの主の女は現代という捉え難い時の全体を意味してもいそうだ。この語はその昔、運動界隈でロゴスとの二項対立的概念としてしばしばいられていた。科学的社会主義の立場から言えば、革命とは人類史を貫く客観的法則から必然であり、それを理性(ロゴス)で把握した主体が実践する。対して、客観的法則が主体における情念(パトス)の爆発で破られる時、非日常的な革命が起こるという主観論を唱える向きもあった。「日常か、非日常か」「マルクス主義か、実存主義か」の対立だ。
当時の先鋭な若者はどちら側に立つかについて、今の「推し活」どころではないシリアスさで対峙していた。その思いが時代を包みこむ巨大なパトスだったとすれば、安倍公房も『砂の女』も、もしかすると掲句もまた、そんな流砂の渦中に存在するのでは、という主観的読み方をついしてみたくなる。
閑話休題。掲句で季語「一月」は新たな年に入ることへの感慨、ある種の情念を帯びる。そこへ、さらさらと味気なく、つかみどころなく、しかしどこか罪深い女がいる。それは男にも即座にすり替わる存在で、安倍公房のいう通り本質は「砂」なのではないか。
無味無臭な砂の持つパトスというアイロニカルな表現と「一月」という季語との響き合いが眼目だろう。そこでは『アラビアのロレンス』で少年を一瞬で吞み込む砂漠の流砂のように、砂が「生きもの」的な情念さえ、かいま見せる。そうしたグレートマザー的な自然とのつながりも射程に捉え、読む者のパトスを巧みに昂らす作劇術(ドラマツルギー)の巧みさを感じさせる一句だ。(了)
